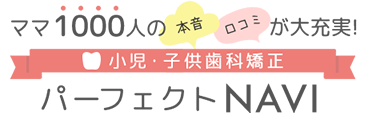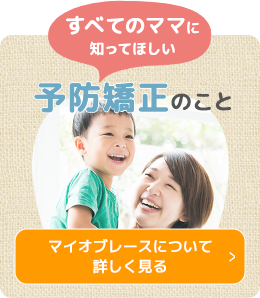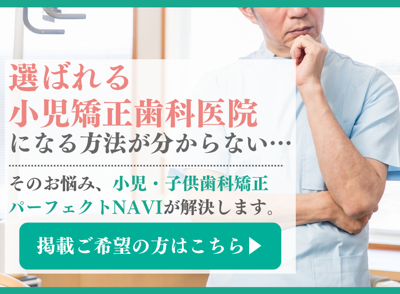[最終更新日]: 2025/03/20
滑舌が悪いのは歯並びのせい?
子供の成長過程で言語機能の発達はとても気になります。幼児期は発音が未熟な時期ですが、5歳から6歳頃になると正確に発音できるといわれています。しかし、この頃に「サシスセソ」や「タチツテト」が上手く発音できない場合は、何らかの原因で発音が難しくなっている可能性があります。本記事では、子供の滑舌がよくない原因や治療について解説していきます。
歯並びは滑舌に影響する
不正咬合(歯並びや噛み合わせに問題がある場合)発音が不明瞭になったり、滑舌が悪くなったりすることがあります。とくに受け口のように上下の歯の嚙み合わせが逆になっていると、発音しにくくなる場合が多く、滑舌が悪く聞こえる原因の一つになります。不正咬合では精密検査で原因を明らかにし、適切な治療法を選ぶことで歯並びの改善だけでなく、発音の問題も解消できる可能性があります。顎の成長段階の早い時期に矯正治療を開始することで、より良い結果が期待できます。ただし、骨格的な問題が大きい場合は、外科的な治療が必要になる場合もあります。
子供の発音の目安
言葉の発達に伴い発音も正確になっていきます。正しく発音できるようになるまでの年齢の目安は以下の通りです。
- 2歳から3歳ころ
母音(ア・イ・ウ・エ・オ)
タ行(タ・チ・ツ・テ・ト)
パ行(パ・ピ・プ・ペ・ポ)
マ行(マ・ミ・ム・メ・モ)
- 3歳から4歳ころ
カ行(カ・キ・ク・ケ・コ)
ガ行(ガ・ギ・グ・ゲ・ゴ)
ダ行(ダ・ジ・ヅ・デ・ド)
- 5歳から6歳ころ
サ行(サ・シ・ス・セ・ソ)
ザ行(ザ・ジ・ズ・ゼ・ゾ)
ラ行(ラ・リ・ル・レ・ロ)
子供の滑舌が悪い原因
子供の滑舌がよくない原因に歯並びの問題が考えられますが、ほかにも「構音器官(こうおんきかん)」のどこかに原因がある可能性があります。構音器官とは「下顎、舌、唇、軟口蓋(なんこうがい)」などの発音に関する器官のことで、これらに問題があると発音や滑舌に影響が出ます。
形に問題がある
生まれた時から唇や舌の形や大きさに異常がある場合、または神経や筋肉に問題があり、発音器官の動きが制限される場合、器官性構音障害(きかんせいこうおんしょうがい)の可能性が考えられます。これは、発音に必要な器官の形や機能に異常があり、発音が適切にできない状態を指します。器官性構音障害の原因としては、唇の閉鎖がうまくいかない鼻咽腔閉鎖不全、舌が小さい小舌症、上顎の天井部分が開いている唇顎口蓋裂などが挙げられます。また、舌の動きを制限する舌強直症や舌癒着症も発音に影響を与える可能性があります。このような器官性構音障害は、発音器官の構造的な問題が原因なので、通常の言語訓練だけでは改善が難しい場合があります。専門家による評価と、場合によっては外科的な治療や、発音訓練が必要となることもあります。
歯並び嚙み合わせの問題
歯並びの乱れである不正咬合は、発音に大きな影響を与えます。受け口、出っ歯、すきっ歯、開咬などの不正咬合は、それぞれ特有の発音の困難を引き起こします。例えば、受け口では下の前歯が前に出ているので、舌を上あごに付けにくくなり、「サ行」の発音が難しくなります。出っ歯の場合は、上の前歯が前に出ているので、唇を閉じにくく、「パ行」などの発音がしにくくなります。すきっ歯や開咬の場合は、歯と歯の間に隙間があるので、空気が漏れてしまい、「サ行」や「タ行」の発音が不明瞭になります。これらは、歯と舌の適切な位置関係が保てないことが原因です。不正咬合によって発音が困難になると、自信の喪失やコミュニケーションの不安につながるおそれもあります。歯並びの治療によって、これらの問題が改善されるケースも多く見られます。
筋肉に問題がある
脳血管障害や脳性麻痺など、神経や筋肉に問題が生じることで発音に必要な器官(舌、唇、顎など)の動きが制限されることで滑舌が悪い症状が出ることがあります。この障害では、発音だけでなく、話し方のリズム、アクセント、話す速さなどにも影響が出ることがあります。つまり、脳からの指令がうまく筋肉に伝わらないことで、言葉を発する際に困難が生じます。
聴覚に問題がある
正しい発音を聞き取ることが難しい場合も発音に問題が生じることがあります。聴覚を通じて得られる発音が正しく聞き取れないため、正しい発音の学習が妨げられ、発音の誤りが修正されにくいためです。発音の正確さだけではなく、イントネーションやリズムといった音声の要素にも影響を受ける可能性があります。主な原因としては、先天性の難聴や後天的な聴力低下などが挙げられます。また、聴覚障害の程度や種類によっても、発音への影響は異なります。
そのほかの問題
身体的な異常がなく、特定の発音を誤って繰り返すことで、発音が定着してしまう場合にも滑舌が悪くなることがあります。周囲の人の発音や環境の影響、個人の学習能力など、様々な要因が影響します。例えば、両親の発音が標準語でない場合や、地域の方言の影響を受ける形で、発音を学習することになります。また、読み書きの遅れや注意欠如多動性障害(ADHD)など、他の学習障害との関連性が指摘されることもあります。
滑舌が悪い場合の聞こえ方
- 口蓋化構音
口蓋化構音(こうがいかこうおん)とは、特定の音、とくに「サ行」や「タ行」などが、「カ行」や「が行」のように、舌の位置が上あごの奥の方に移動してしまい、こもったような音になる発音障害です。この発音の異常は、口蓋(上あごの奥の部分)の形態や機能に原因がある可能性があります。それ以外にも、口蓋前方部の狭窄や反対咬合などによる場合があります。
- 側音化構音
側音化構音(そくおんかこうおん)では、正常な発音のように空気が口の中央を通って発音されるのではなく、舌が左右どちらかに偏り口の端から空気が漏れるように発音されます。このため、「し」「ち」などの音が「ヒ」「キ」のように聞こえ、聞き取りにくくなります。舌は通常、口の中央を基準に動きますが、側音化構音では舌が左右どちらかの歯や顎に強く押しつけられ、舌の動きが制限されている状態です。
- 鼻咽腔構音
発音する際に鼻から過剰に空気が漏れてしまい、「い」「う」などの音が「ん」や「くん」のように鼻濁音に変化してしまう発音の誤りを指します。例えば、「イス」が「ンス」のように聞こえるなど、言葉が聞き取りにくくなり、とくに幼い子供にとっては、コミュニケーション障害につながる可能性があります。
- 声門破裂音
声門破裂音とは、声門を閉じて息を溜め、それを急に解放することで発音される子音の一種で、声門閉鎖音とも呼ばれます。咳払いの「ッ」のような音に例えられます。
- 咽頭破裂音
咽頭破裂音とは、舌の根元を喉に押しつけることで起こる破裂音の一種で、「カ」行の音によく見られます。咳払いのように聞こえます。
- 咽頭摩擦音
舌根や仮声帯を咽頭後壁が狭まって作られる摩擦音で、咳払いのように聞こえます。
滑舌が悪いままだとどうなるの?
子供の滑舌が悪い原因は、ご紹介したようにさまざまです。これらを放置した場合、発音の困難はもちろん、咀嚼機能の低下による消化不良、むし歯や歯周病のリスク増加、顎関節症、肩や背中の筋肉の緊張、そして精神的なストレスなど、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。これらの問題が複合的に作用することで、子供の成長発達に悪影響を及ぼす恐れがあるので、滑舌が悪い症状が見られた場合は、原因をはっきりとさせ、治療を行うことが重要です。
どのような治療があるの?
歯列やかみ合わせに問題がある場合は、歯科矯正治療や口腔筋機能訓練を行い、舌の動きや位置を改善することで発音を改善します。鼻咽腔閉鎖不全には、スピーチエイドなどの補助装置の利用や、矯正治療で口腔構造を整えることで改善が期待できます。運動や聴覚に問題がある場合は、小児科や耳鼻咽喉科、言語聴覚士と連携して治療に当たります。
滑舌が悪い場合は原因を明らかに
これまで紹介してきたように、子供の滑舌が悪い原因には、さまざまなものがあります。時期が来ても滑舌がなおらない場合には、早めに原因を明らかにして、原因に対応した治療をおこなう必要があります。まずは、お近くの歯科クリニックや病院に相談してみましょう。